
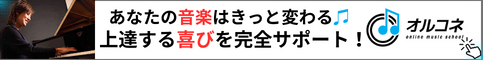
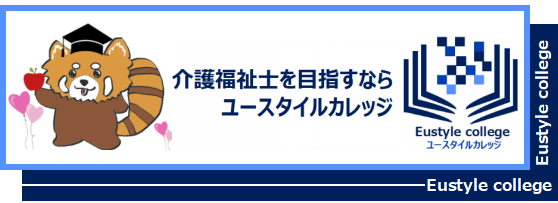
1968年7月にリリースされたマイルス・デイヴィスのスタジオアルバムです。なぜか「鳥よけ」にしか見えないジャケットデザインがまた強烈に印象に残ります。
エレクトリック・マイルス の出発点と言われており、このアルバムからエレクトリック・ベース、エレクトリック・ピアノが使用され始めました。
また、この後やってくるフュージョンで大ブレイクするエレクトリックギターのジョージ・ベンソンも1曲参加しています。
知っている限りではマイルスがバンドでギターを使いはじめるのはここからです。
ベンソンのプレイがこのアルバムにどれくらい貢献しているかはイマイチわかりませんが、明らかにここから電化マイルス のギターの重要度が増してきました。のちにはジミ ・ヘンドリクスとの共演を熱望します。
マイルスとジミはお互いに意識していて、ジミが亡くなるまでに1度は共演があったようですが記録として残されている様子はありません。
共演するギタリスト、ジョン・マクラフリンやマイク・スターンなどにも「ジミ ・ヘンドリクスのように」と注文をつけていたことも有名です。
このアルバムを象徴するのが最初の曲「スタッフ」です。リズム、フレーズともにそれまでのジャズにはないものを感じさせます。
ここで聞かれるのはリズムに合わせたテーマメロディですので、わかりやすくかっこいいものです。
この後、電化マイルスは膨張を続け、エレクトリックな楽器を多用したリズム重視の時期になっていきます。
そこについては前から感じていたことがあるのです。
エレクトリック・マイルスの場合、ファンクを演っても自然に体が動くなどというようなノリではありません。リズムは抜群にいいのですがグルーヴ感が異質なのです。聴いていて勝手に腰が動いて踊り出すというような肉体的ダンスミュージックではありません。
パイオニア精神旺盛なマイルス としては「いや、そういう単純なのはもう他が演ってるから」ということなのでしょう。
マイルスの場合は体で感じるのではなく、心(頭)で感じる音楽です。バンドメンバーは全員同じリズムではなく、基本のリズムから各自が細分化して演奏しています。そういうところがが時間を超越して飽きないところかもしれません。(個人の感想です)


アルバム「マイルス・イン・ザ・スカイ」のご紹介です。
演奏
マイルス・デイヴィス トランペット、コルネット
ウェイン・ショーター テナーサックス
ロン・カーター ベース、エレクトリック・ベース
トニー・ウィリアムス ドラムス
ハービー・ハンコッック ピアノ、エレクトリック・ピアノ
ジョージ・ベンソン エレクトリック・ギター Tr.2

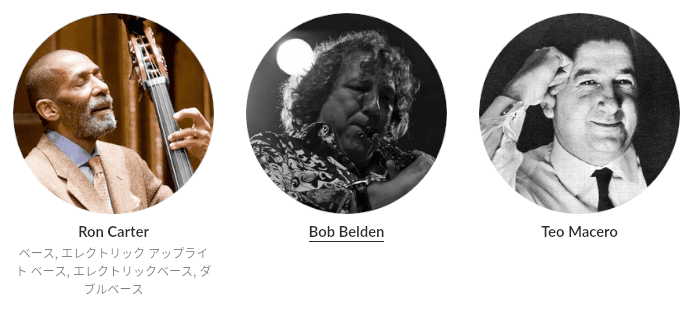
曲目
*参考までに最後部にyoutube音源をリンクさせていただきます。
1, Stuff スタッフ
(作 マイルス・デイヴィス)
最初に聴いた時、普通にカッコイイ音楽だなあと思いました。テーマはメロディアスで聴きやすいものです。素直にリズムに乗れます。
で、最高にいいのがトニー・ウィリアムスのドラムです。この人は本当に天才です。この時期のマイルスはドラムを聴いているだけでも十分に楽しめます。
2, Paraphernalia パラフェルナリア
(作 ウェイン・ショーター)
訳せば道具一式となります。ハードバップマナーの曲をリズムから壊して行こうとしています。
3, Black Comedy ブラック/コメディ
(作 トニー・ウィリアムス)
ドラマーのトニー・ウィリアムスの曲です。前2曲に比べれば今までのアコースティックジャズのフォーマットを掘り下げている感じです。全員安心して乗って演奏していますが、さすがドラムのフィル・インがすごい、煽りまくります。
4, Country Son カントリー・サン
(作 マイルス・デイヴィス)
これもアコースティック路線です。マイルスがトランペットではなくコルネットに換えて吹きまくります。途中何度か叙情的なメロディが顔を出します。
5, Black Comedy ブラック/コメディ
(作 トニー・ウィリアムス)
ドラムを聴いているとこっちの方が面白い気もします。最初からイケイケと煽ってます。でも曲全体はTr.3の方が音が厚いか。
6, Country Son カントリー・サン
(作 マイルス・デイヴィス)
同じ曲とは思えないほどこちらのテイクは静かに始まります。ウェイン・ショーターがコルトレーンみたいなフレーズを吹いたりします。
録音エンジニアがジャズ録音の人なので、エレクトリックベースでも音がこの時代のジャズマナーで録音されているのでしょうか。
欲を言えばベースがもっと大きければ、ドラムとの絡みでもっともっと楽しめるのに・・・と思ってしまいました。
でもそれは小さなことです。総じて音がリアルで、さすが名盤です。


コメント