

1979年、いきなりとんでもない大ヒット、世界中を席巻したアルバムがリリースされました。
イギリスのバンド、スーパートランプによる「ブレックファスト・イン・アメリカ」です。
世界中で大ヒットとなり、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ドイツ、フランス、ノルウェーなどでチャートの首位となりました。
日本でもアルバムタイトル曲をはじめ、「ロジカル・ソング」や「グッドバイ・ストレンジャー」などがヘビーローテーションでオンエアされていました。
なんと言ってもアルバムジャケットに登場するハンバーガーショップのおばさんまでもスターになる始末です。
私は今だにこのアルバムの曲を聴くとその時代がはっきりと蘇ります。
これが時代を写すポップス、軽音楽のいいところだと感じます。
今では情報が細分化され格段に多くなっているので、そういう感覚をみんなが共有することはもうないのかもしれません。
スーパートランプはイギリス出身のプログレッシヴ・ロックに分類されるバンドです。
この6枚目のアルバムで大ブレイクするまではマニアックなファンのみぞ知るようなバンドでした。
個人的な思い出としてはその頃(1970年代後半)のミュージック・ライフ誌のカタログ広告です。
「消えない封印」や「クライム・オブ・センチュリー」などがフリートウッド・マックの「英国の薔薇」やパリス、ハンブル・パイのアルバムと一緒に掲載されていました。
なので名前くらいは知っていたのですが、マニアックな音楽なんだろうなあと思っていたものです。
「消えない封印」に至っては露出したバストに刺青というジャケットからして親に見せられないようなシロモノでしたしね。
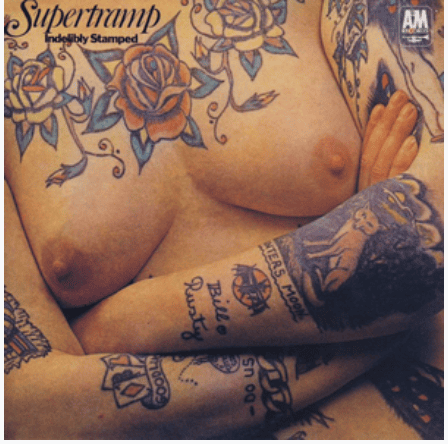
スーパートランプはイギリス出身のバンドですがアメリカ、ロサンゼルスに活動を移してこの「ブレックファスト・イン・アメリカ」をレコーディングしています。
プログレッシブな感覚とアメリカンポップスがうまく融合したアルバムと評価されました。
通常だとこれくらい大ヒットを記録すると、大物バンドの仲間入りをしてしばらくは売れ続けていくものですが、残念ながらこの後は何事もなかったように失速してしまうのでした。
なぜかと考えると、まず通常のロックバンドと違ってギター中心ではなくキーボードが主体だったことが挙げられます。
1970年代の名だたるロックバンドのようにヴォーカルの次に顔となるような名ギタリストはいませんんでした。
キーボード主体といえばエルトン・ジョンやビリー・ジョエルなどが挙げられますが、バンド単位だとELPとユーライア・ヒープくらいしか思いつきません。
それとバンドメンバー全員、なんかオタクっぽくてイケメンもいなくてスター性とかカリスマ性とかの大物のオーラがなかったこと・・ではないかと思われ・・・、ってなんですか、そういうこと言ってはいけませぬ。
そこがいいという人も一定数いたとは思いますが。
ということで元のマニアックなバンド、ニッチな世界にに戻ってしまいました。
なぜかその位置が似合うバンドでもあります。

(以下、Wikipediaより引用)
このアルバムは一体どうしてしまったのかと思えるほど名曲のオンパレードです。
音楽評論家のスティーヴン・ホールデン氏は「このアルバムは以前の曲がりくねったジェネシス(プログレッシブ・バンド)のような難解な断片を改善し、準シンフォニックな古典主義とロックンロールの間で可能な限り巧妙にバランスをとった、ポスト・ビートルズのキーボード中心のイギリスのアートロックの教科書的なアルバムだ。
ここに収録されている曲は並外れてメロディアスで簡潔に構成されており、1977年にロサンゼルスに移って以来、これらのミュージシャンがアメリカのポップスに浸ってきたことを反映している。
と評しています。
(引用終了)
まさに言い当てていると思います。
スーパートランプは1968年にイギリスでキーボード・プレイヤーのリック・デイヴィスが創設しました。
メンバー募集でロジャー・ホジソン(ヴォーカル、ギター)が加わってこの二人を中心に1969年から活動していきます。
基本的にはこの二人が曲を作り歌っていくこととなります。
バンド名はリックが好きだった小説家ウィリアム・ヘンリー・デイヴィスの「素晴らしき放浪者の自叙伝」から撮ったものだそうです。
原題は「The Autobiography of a Super-Tramp」です。
同名のスーパートランプのベスト盤もあります。
最初はプログレ色の強いバンドでしたが徐々にポップな面も出していきました。
リックとロジャー以外のメンバーを一新して制作した1974年のサードアルバム「クライム・オブ・センチュリー」は全英4位、全米38位とヒットし、「危機への招待(75年)」「蒼い序曲(77年)」と順調に売り上げを伸ばしていきます。
(イギリスではトップ20以内には入りました。といいつつも日本ではまだまだ無名な存在でした)
そして1979年、世界的な社会現象となる「ブレックファスト・イン・アメリカ」がリリースされるのでした。
アルバムジャケットも印象深いものです。
飛行機の窓からみたマンハッタンの手前に本当ならありえない位置で自由の女神と同じようなポーズのウエイトレスが写っています。
この人はケイト・マータグという俳優、コメディアンだそうです。
1980年のグラミー賞でジャケット部門とエンジニアリング部門を獲得しました。
確かに優秀な録音だと思います。
アナログっぽい音で今聞いてもアナログ音源の気持ちよさが伝わってきます。
収録曲は全てリックとロジャーによって書かれています。
また自分の書いた曲は基本、メインヴォーカルをとっています。
低音で力強う方がリック・デイヴィスで若干ハスキーで高い声がロジャー・ホジソンです。
この時期、二人は仲が悪かったらしく、作った曲を見てもお互いに逆張りしているような内容にさえ感じられます。
そういうバンド内が不安定な時の方が毎晩が作られやすいという不思議な面もあります。
後期のビートルズを筆頭にキング・クリムゾンやイエスもそうでした。
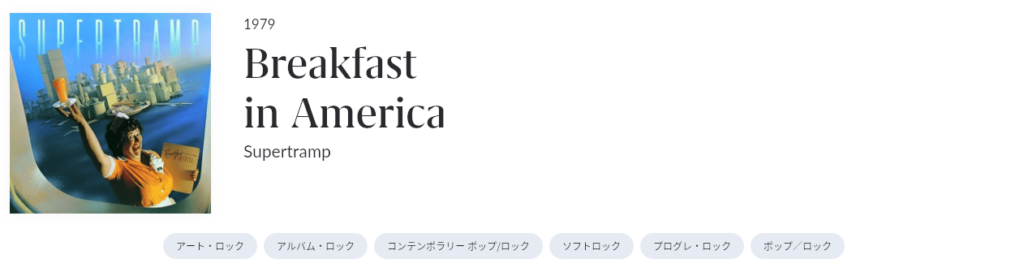
アルバム「ブレックファスト・イン・アメリカ」のご紹介です。
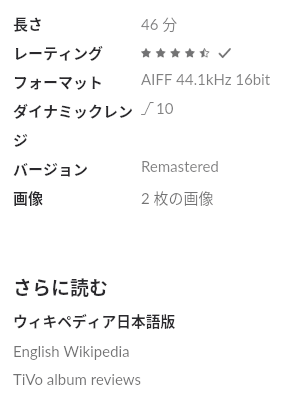
演奏
スーパートランプ
リック・ディヴィス ヴォーカル、キーボード(Tr.2でのクラヴィネットを含む)
ロジャー・ホジソン ヴォーカル、キーボード、ギター(Tr.2での12弦ギターを含む)
ジョン・ヘリウェル 木管楽器
ボブ・シーベンバーグ ドラム
ダギー・トムソン ベース
ゲスト・ミュージシャン
スライド・ハイド チューバ、トロンボーン
ゲイリー・ミールケ オーバーハイム・プログラミング
プロダクション
ピーター・ヘンダーソン プロデューサー、エンジニア
スーパートランプ プロデューサー
レニス・ベント アシスタント・エンジニア
ジェフ・ハリス アシスタント・エンジニア
グレッグ・カルビ リマスター(2002)
ジェイ・メッシーナ リマスター(2002)
ラッセル・ポープ コンサート音響エンジニア
マイク・ダウド アートディレクション、カバーアートコンセプト、アートワーク
ミック・ハガディ アートディレクション、カバーデザイン
マーク・ハナウアー 写真
アーロン・ラポポート 表紙写真


曲目
*参考までにyoutube音源をリンクさせていただきます。
1, Gone Hollywood 憧れのハリウッド
(リック・デイヴィス)
スターを夢見てハリウッドに来たけれど、さっぱりうまくいかに男の歌です。
遠くでかすかに聞こえるピアノがフェイド・インして始まります。
ドラマチックながらポップ感とプログレ感がマッチして聞きやすい曲調です。
ソロはサックスが大きな位置を締めています。こういうサウンドがAORっぽく時代的に受けたのかもしれません。
2, The Logical Song ロジカル・ソング
(ロジャー・ホジソン)
名曲です。印象的なメロディが一日中頭の中で繰り返されます。
1曲目に続いてサックスのソロも登場します。
「若かった頃、人生はとても素晴らしいものに思えた。奇跡のようで、美しく、魔法のようだった」と始まります。
「でもその後、彼らは私に分別を身につけることを教えるために遠くへ送り出した」
「論理的で、責任感があり、実践的であること」
「そして私がとても頼りになる世界を見せてくれた。臨床的で、知的で、皮肉屋だった」
と大人になっていくことを歌います。ロジャー・ホジソンの声質が曲にとってもマッチしています。
3, Goodbye Stranger グッドバイ・ストレンジャー
(リック・デイヴィス)
過去を振り捨てて前進しようとする歌です。「ストレンジャー」とは行きずりの人という意味です。
ピアノで始まるイントロがすごくいい流れだと思います。
2:30あたりからの展開が時代性もあっていい感じです。
4, Breakfast in America ブレックファスト・イン・アメリカ
(ロジャー・ホジソン)
これも相当に名曲で、当時は1日中頭の中でヘビーローテーション状態でした。
5, Oh Darling オー・ダーリン
(リック・デイヴィス)
これまたシングルカットすればヒットしそうな曲です。
ミディアムテンポでピアノ中心のサウンドは思いっきり気持ちのいいアレンジです。
6, Take the Long Way Home ロング・ウェイ・ホーム
(ロジャー・ホジソン)
打って変わってピアノの重低音から始まりプログレ感が滲み出ていますが、次第にポップな展開になります。。
ハーモニカがいい雰囲気を出しています。
7, Lord Is it Mine 全ては闇の中
(ロジャー・ホジソン)
ポップで情感溢れる詩ぼ世界です。
「全てが暗く、何もかもうまくいかない時は、勝つ必要はなく、戦う必要もない」という内容です。
ロジャー・ホジソンの世界です。
8, Just Another Nervous Wreck 神経衰弱を吹き飛ばせ
(リック・デイヴィス)
今度はまた違ったリック・ディヴィス世界です。
「奴らは発見したら逃げ隠れするだろう
誰もが今は神経衰弱
人生はただのつまらないもの、奴らはお前の番号を知っている 俺たちは
今、受けた分だけ返してやる
どん底から立ち上がり、お互いに固執する 奴ら
を限界まで追い詰めてやる、今、
奴らは血を流すだろう、それが奴らに必要なことだ
俺たちは集まって奴らの正体を暴く」
ここではポジティヴな姿勢が見られます。リック・デイヴィスの世界です。
9, Casual Conversations 退屈な会話
(リック・デイヴィス)
ほのぼのとした曲調ですが、意思疎通ができない悩みを歌っています。
10, Child of Vision チャイルド・オブ・ビジョン
(ロジャー・ホジソン)
最後らしく7分を超える対策です。
ただ強弱の多いプログレ風のドラマチックな展開ではなく、ポップでリズミカルに進んでいきます。
お互い間違っていないんだけど、うまくいかないよねえというロジャーがリックに対して歌いかけているような内容です。
このアルバムに関しては中心の二人の軋轢がいい方向に作用して創作に向かっていったのだと改めて感じます。
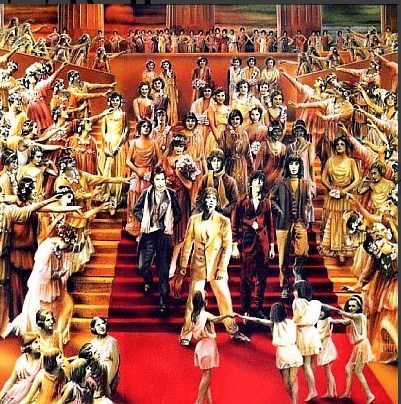
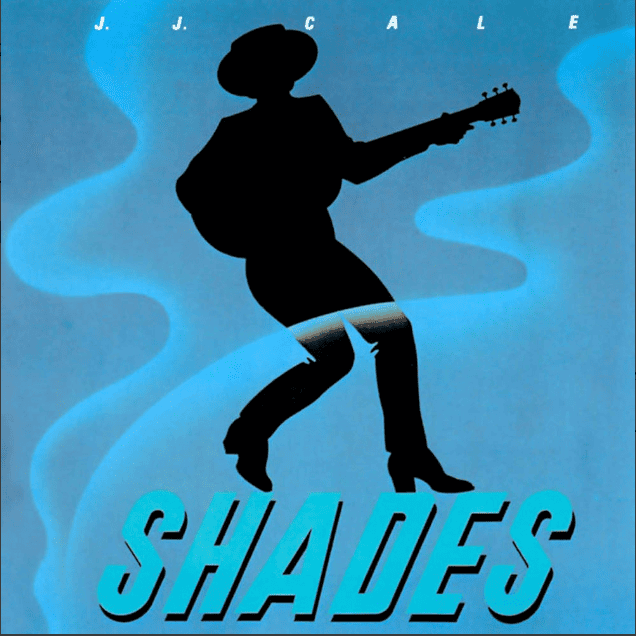
コメント